さわやか社員の皆さん、こんにちは!お元気ですか!いつもありがとうございます。折に触れて届く皆さんからのお葉書はとても嬉しく、勇気づけられています。 「朝晩の涼しさに秋の気配を感じる季節となってきました。毎年、誕生日祝い…
№108 温かく誠実なチーム医療を通じて地域生活者の健康ベストパートナーへ‼

令和7年7月29日(火)
医療法人社団 厚済会 会長 花岡 加那子 様
生い立ちと転機
― 花岡会長の生い立ち、学生時代のエピソード、大きく影響を受けたことや転機となったことをお聴かせください。―
私は生まれも育ちも横浜で、親戚一同が医師という医療家系に育ちました。
特に祖父には大変可愛がってもらい、おじいちゃん子で、物心ついた3歳の頃には、将来は医師以外の職業を考えたことが無いような子供でした。祖父は四国の愛媛県新居浜市で開業しており、夏休みなどに遊びに行くと、常に患者さんのために駆け回っている姿を間近で見ていました。敷地内に診療所があり、患者さんに呼ばれればすぐに駆けつける、その姿が私にとって「働く」ということの原風景でした。
祖父は自分の体調が優れない中でも、患者さんのために尽力していました。私が6歳になったまさにその誕生日に、祖父は亡くなったのですが、おじいちゃん子だった私にとって、それは非常に衝撃的な出来事であると同時に、祖父からバトンを渡されたような感覚を鮮明に覚えています。この経験が、医師を目指すという思いを一層強くしたのだと思います。
父もまた、仕事一筋の人間で、小学生の頃、夜11時頃に終わる塾の帰りに父のクリニックへ寄り、一緒に車で帰宅するのが唯一会える時間でした。家族旅行の記憶もなく、高校生になってようやく一緒に外食をしたくらいです。でも、それが当たり前の日常でした。

一方で、両親は四国の出身ということもあり、「女の子は仕事をするものではなく、一歩下がって家庭を守るものだ」という考えが非常に強い家庭でした。成長するにつれて、独立心が強く好奇心旺盛だった私はその考えに反発し、「自分で稼いで家を出て独立するしかない」と考えるようになりました。両親に内緒でアルバイトに明け暮れ、家出をしては捜索されるような、心配ばかりかける子供だったと思います。
中学からは私立の女子校に通いましたが、男子と殴り合いをするような活発な性格だったため、女子だけの環境は性に合わず、鬱憤が溜まる一方でした。高校時代も、海外留学の夢を「女の子だから危ない」と反対され、「ならば自力でお金を貯めて行こう」と決意していました。とにかく、意義のある生き方を見出したいと強く思っていました。
厚済会入職の経緯と当時の経営状況について
― お父上が設立された厚済会に入られた経緯と、入職された当時の経営状況について、多くの反発があっても逃げずに真正面から伝え続けた強い信念はどこから生み出されたのかをお聴かせください。―
医師になること以外考えられなかったものの、看護大学や社会福祉の道も経験しましたが、どれもしっくりきませんでした。この家にいては自分のやりたいことは実現できないと考え、両親の目の届かない遠い場所へ行こうと、静岡県浜松市の大学へ進学しました。大学卒業後、教授の推薦で伊豆にある某大学大学病院の地域連携室立ち上げに携わる話があり、そこでお金を貯めようと考えていました。
ところがその矢先、またしても私の誕生日に、今度は父が心肺停止で倒れました。その時まで、親不孝を重ね、一刻も早くこの家から解放されたいとさえ思っていたのですが、祖父の死を彷彿とさせる出来事に、やはり家族が一番大事なのだと痛感しました。幸い父は一命を取り留め、回復してきた頃、「一年だけでいいから、そばにいて一緒に働いてほしい」と頼まれました。やはり心配でもありましたし、そばにいたいという気持ちもあり、その言葉を受け入れて厚済会に入職することを決意しました。
そうした経緯で入職したものの、父が私に期待していたのは、後継者としての働きではありませんでした。そのため、入職から10年ほどはずっと平社員のままで、最初の配属は外来の看護師でした。周りから見れば、跡を継ぐわけでもないのに、何かと口を出してくる厄介な存在だったと思います。
しかし、組織が大きくなる中でその理念は薄れ、医療安全が自分たちを守る言い訳に変化している態度や姿勢が目に余りました。患者さんからのクレームに対し、「うるさい患者だ」と捉える職員も少なくなく、私はいてもたってもいられなくなりました。
ただの一職員が「何を考えているのですか」と意見しても、それは批判としか受け取られません。そこでまず、患者さんのことを少しでも理解してもらおうと、入職後すぐに「地域連携室」を勝手に立ち上げました。今思えば生意気な若者でしたが、患者さんのご自宅や介護施設などを訪問し、その生活環境を見ることで、医療者としての本来の優しい気持ちを思い出せるのではないかと考えたのです。
時間を見つけては様々な部署を回り、「あそこはどうなっているんだ」と見て回る私は、相当煙たい存在だったでしょう。患者さんからのクレーム対応も「やるならお前がやれ」と全て私に回ってきましたが、それを一つひとつ対応し、患者さんの声をスタッフと共有していくうちに、次第に「この子は少し使えるかもしれない」と、スタッフ側からの要望も寄せられるようになっていきました。
しかし、組織全体の改革は困難を極めました。院長たちに改善を訴えても「現場も知らないくせに口を出すな」と門前払いです。父に相談しても「お前にそんなことは望んでいない。みんな頑張っているのだから首を突っ込むな」と突き放される始末でした。
経営を学んだこともなく、ただ理想を叫ぶだけだった自分は、今思えば未熟だったと反省しています。既存の組織を変えることの難しさを痛感し、それならば「コンセプトを明確にした新しい病院を一から立ち上げれば、理想の医療を実現できるのではないか」と考えるようになりました。折しも15年ほど前、横浜市で病床整備の計画があり、私は独断で病院立ち上げに向けて動き始めました。

当然、院長たちからは大反対されましたが、6年もの歳月をかけて説得を続け、最後は「これが実現できないのなら、ここに未来はないので辞めさせていただきます」と半ば脅すような形で、ようやく了承を得て、現在の横浜じんせい病院を立ち上げるに至ったのです。
この間、組織の作り方や経営について学ぶ必要性を痛感し、ビジネススクールに通い始めました。そこで出会ったのが、「経営品質」の考え方です。2005年日本経営品質賞を受賞された望月広愛教授より顧客価値経営について学び、この考え方を自組織に導入すれば組織改革に繋がると直感しました。
2017年から、各部署の責任者を集め、研修という名目で毎月1回、対話の場を設けました。「素晴らしい組織とは何か」「自分が患者ならどんな病院に行きたいか」といったテーマで議論を重ねるうち、皆の視点が徐々に患者さん、つまり顧客の視点へと変わっていったのです。いくら指導的に「こうすべきだ」と言っても、人の心には響きません。自分たちで考え、対話し、心から「そうしたい」と腹落ちして初めて、組織は変わっていくのだと、数々の失敗を通じて学びました。
なぜそこまで信念を貫けたのかと問われれば、やはり祖父や父の存在が大きいです。彼らが患者さんへ真摯に向き合う姿を間近で見て育ち、人のために尽くすことの尊さを肌で感じてきました。それが、自分にとっての「生きる道」であり、「生きた証」なのだと思っています。「ただ何となく生きて死ぬのは絶対に嫌だ」「世の中や人の役に立って死にたい」という思いが、常に心の中心にありました。
また、医師になることを反対され続けたことで、「医療はこうあるべきだ」という理想像や渇望が、人一倍強くなっていたのかもしれません。その強烈な「あるべき論」が、様々な圧力に屈しない原動力になっていたのだと思います。経営品質を学びながら、最近ようやく、「あるべき」ではなく私達がありたいと願う想いを語り合い育むことが一番大切であると実感しています。
厚済会が提供する価値と強み
― 2023年度日本経営品質賞推進賞で評価された3つの顧客価値提供についてお聴かせください。―
2023年度の日本経営品質賞で評価された3つの価値について、これらは経営品質活動の中で磨かれたものもあれば、元々取り組んでいたものもあります。
「チーム医療の推進」は、入職当初から最も意識してきたことです。職員同士がバラバラで、同じグループ内の施設で緊急事態が起きても誰も助けに行かないという現実に強い衝撃を受けました。職人集団である医療者は、それぞれが高い能力を持っていても、目的が共有されていなければ力は分散してしまいます。お互いの力を掛け合わ
せ、より大きな価値として患者さんにお届けするために、部署や施設の垣根を越えたコミュニケーションの機会を積極的に設けてきました。
「近隣医療機関とのネットワーク」は、もともと横浜市立大学出身の父が築いた人脈が土台にありますが、それに甘んじることなく、私自身が師長たちを連れて挨拶回りを重ね、顔の見える関係を地道に構築してきました。大学病院の先生方が研究を行う際には、症例データを提供するなど、お互いがWinWinになる関係づくりを心がけています。緊急時に患者さんを助けていただくからこそ、平時から私たちが貢献できることを続ける。その積み重ねが、現在の強固な連携につながっています。
「地域密着型の施設運営」という点では「あおぞら会(患者会)」での取り組みも、長年の継続の賜物です。17年前は、会合がまるで「恐喝の場」のようになってしまうほど、患者さんと医療者の関係は良好ではありませんでした。しかし、当時の患者会の会長さんとも真摯に話し合いを重ね、「患者さん自身も透析しながら元気に生きる努力をすること」「お互いにできることとできないこと」を共有し、共に「病気があってもいきいき生きる」を目指すパートナーとしての関係を築いてきました。今では、バス旅行で一緒にいちご狩りに行ったり、温泉旅行に出かけたりするまでになっています。こうした場でこそ、アンケートでは決して得られない、宝物のような患者さんの本音を聞くことができるのです。
花岡会長を支える経営チーム
― 花岡会長を支えるチームをどのように創り上げてこられたのか、経営品質活動とどのように繋がっているかをお聴かせください。―
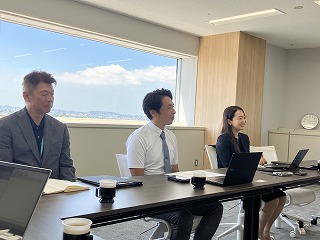
特定の「経営チーム」という区切りはありません。本日同席している鎮目事務長や貝澤部長をはじめ、多くの職員が「どうすればもっと良くできるか」を常に考え、行動してくれています。
その土台となるのは、やはり2017年より取り組んできた顧客価値経営の考え方ですが、2023年より更にそれを実践できるチームとなるために、人財共育に投資し組織開発を進めています。具体的には「システムコーチング」や「リーダーシップ開発」を導入し、現在管理職層を中心に約60名がこのトレーニングを受けています。一人ひとりにコーチがつき、チームとは何か、自分自身がチームにどう影響を与えるかといった「チーム力学」を学んでいます。研修では、協力しなければ達成できない課題などを通して、成功や失敗を擬似的に体験します。なぜこのチームは失敗したのかを深く振り返ることで、目標へのコミットメントの重要性などを、知識としてではなく「体感」として腹落ちさせていくのです。
教えるというよりは、頭と体をフル稼働して、体験から発見したものと理論をつなぎ合わせることでチームと個のそれぞれの成長を促進させたいと思っています。こうした実践的な研修を通して、苦しい経験や痛い思いをしながらも、皆がリーダーとして成長してくれていることが、組織の大きな力になっています。
新日本ビルサービスの評価と期待
新日本ビルサービス様とのご縁は、2023年の経営品質賞の会食で同じテーブルになったことがきっかけでした。その時から社長の志に惹かれ、「ぜひうちの清掃に入ってもらえないか」と願っていましたので、念願が叶い、大変感謝しております。
以前は、院内の床を雑巾がけすると真っ黒になるほどで、清掃が行き届いているとは言えない状態でした。しかし、貴社に入っていただいてからは、床は輝き、院内は清々しい空気に満たされています。「これこそがありたい姿だ」と、その爽快感に感動しました。清潔な環境は感染対策の基本であり、いくら言葉で説明しても分からなかった職員が、美しくなった空間を目の当たりにして「会長が言っていたのはこういうことだったんですね」と理解してくれたのです。これも、環境が人を変えるという実体験でした。
さらに素晴らしいのは、誰が作業をしても同じ品質が保たれる「仕組み」です。以前は「この人たちには難しいのではないか」とさえ思っていた清掃業務が、これほどまでに見違えるとは、正直驚きました。運用体制の構築から実装まで、横浜支店の皆様が本当に親身になってご提案くださり、今では来院される方々から「きれいな病院ですね」とお褒めの言葉をいただくことが増えました。貴社の卓越した仕事ぶりには、学ぶべき点が本当に多いと感じています。これからも、お互いに切磋琢磨し、高め合える関係でいられることを期待しております。

仕事と人生で大切にしていること
現代の医療業界は非常に厳しい状況にあり、日本の医療が持つ、真面目で、丁寧で、一途といった素晴らしい資質が失われかねない環境にあると感じています。私の人生のテーマは、その日本人の素晴らしい資質を守り、慈しみ、育てていくことです。
溢れる情報の中で、本来の人生の意味を見失いがちな現代だからこそ、せめて私たちの小さな医療法人からでも、関わる人々にとって何が大切なのかを伝えていきたい。真摯に、誠実に、謙虚に患者さんを想い、患者さんからも信頼と感謝をいただく。その関係性こそが、自分たちの幸せや人生の彩りにつながるのだということを、守り広げていきたいと考えています。
私は後継者という立場ではないからこそ、この考え方が属人的なものではなく、仕組みや文化として組織に根付き、継続していくことが何よりも重要です。スタッフ一人ひとりが人生の意味を謳歌し、意義ある人生を送れる環境を整えること。それが私の責務であり、人生の意味だと考えています。

厚済会の夢とビジョン
現在、近隣の老舗があった場所を買い取り、地域の皆様が気軽に立ち寄れる新しい医療施設の開設を計画しています。目指すのは、ただのクリニックではなく、訪れるだけで日頃の疲れが癒やされ、自分の体をいたわりたいと思えるような「ヘルス・パワースポット」です。2027年4月のオープンを予定しており、庭でお茶が飲めるような、心休まる空間にしたいと考えています。
10年、20年先を見据えたビジョンとしては、まず、現在通院されている透析や慢性疾患の方達が、365日24時間、生涯にわたって安心して過ごせる体制を盤石に守り抜いていきます。
その上で、今後は「予防医療」にさらに力を入れていきます。これまで培ってきた地域連携の強みを活かし、横浜市や神奈川県、さらには他企業とも連携して健康データを解析し、病気になる前の段階から介入していく取り組みを進めています。日本の医療費高騰の抑制にも貢献できると考えています。
また、治験なども積極的に受け入れ、新たな治療法の開発にも貢献できるような、社会に開かれた医療機関を目指していきたいと考えています。これまで以上に地域の皆様の「人生のベストパートナー」となれるよう、これからも挑戦を続けてまいります。
magazine
社内報
新日本ビルサービス 社内報109号 2025年12月10日 32頁 1, 社長メッセージ2, 事業所紹介シリーズ センコーグループ 浦和物流センター 様3, 新日本グループ創立記念式典・永年勤続表彰4, さわやかインタビ…
当社は、さいたま市の“さいたまロードサポート制度”に参加し、本社近くの東大宮駅前メインストリート沿いで花壇の維持管理を行っています。 ↑見沼区の職員さんご協力のもと、お花を1つずつ植えていきます。 5月・11月に花の植え…
令和7年7月29日(火) 医療法人社団 厚済会 会長 花岡 加那子 様 生い立ちと転機 ― 花岡会長の生い立ち、学生時代のエピソード、大きく影響を受けたことや転機となったことをお聴かせください。― 私は生まれも育ちも…
company
会社案内
recruit
採用情報
資料ダウンロード
新日本ビルサービスのビルメンテナンス・
感染対策清掃・施設運営などにご興味をお持ちの方のために、
サービス内容をまとめた資料をご用意しております。




