さわやか社員の皆さん、こんにちは!お元気ですか!いつもありがとうございます。折に触れて届く皆さんからのお葉書はとても嬉しく、勇気づけられています。 「朝晩の涼しさに秋の気配を感じる季節となってきました。毎年、誕生日祝い…
№108 ~さらに夢を追いかけて未来を拓く~
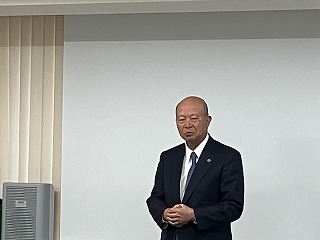
全体会議ご講話
令和7年4月16日㈬
弁護士法人 梅ヶ枝中央法律事務所 代表 山田 庸男 様
生い立ち
私は昭和18年、戦時中に生まれ、父は私が1歳になる前に南方の輸送船で戦死しました。そのため、父の顔を知りません。母は当時不治の病とされた肺結核を患い、入退院を繰り返す生活でした。当然、家計は苦しく、私は小学校4年生から新聞配達をして家計を助けました。しかし、当時は誰もが貧しい時代でしたから、特に肩身の狭い思いをした記憶はありません。
その母が口癖のように私に言い聞かせた三つの言葉があります。一つ目は「貧しいことは恥ではない」、二つ目は「心の貧乏はするな」、三つ目は「人に後ろ指をさされることをするな」。この言葉が、私の生き方の根幹を成しているように思います。私は長屋で育ち、近所の人々に助けられながら生きてきました。中学や高校の先生、大学時代に働いていた会社の上司など、多くの方々の理解と支援があったからこそ、弁護士になることができたのです。
こうした経験から、私は社会的に弱い立場の人々の味方になりたいという思いで弁護士の道を歩み始めました。人間は皆、裸で生まれ、最後は骨となって土に還ります。「本来無一物」という言葉の通り、この世で得たものをいかに社会に還元するかが重要だと考え、60 歳を過ぎた頃から具体的な行動を起こすことを決意したのです。
人生における失敗と「生かされている」という実感
人生がそうであるように、事業もまた平坦な道ばかりではありません。クレームや事故、時には企業の信用を揺るがす不祥事も起こり得ます。
しかし、私が重要だと考えるのは、失敗を恐れないことです。何もしないでその場に留まるより、挑戦して失敗する方がはるかに価値があります。ここで「反省しても後悔はしない」という言葉についてお話ししたいと思います。人生において失敗はつきものですが、その後の向き合い方には「反省」と「後悔」の二通りがあります。後悔とは、努力不足が原因の失敗に対して「もっと頑張ればよかった」と嘆くだけで、次への教訓となりません。一方、反省とは、たとえ精一杯努力しても結果が伴わなかった際に、その原因を突き止め、次の挑戦への糧とする建設的な行為です。私自身、これまでの人生で後悔したことは一度もありませんが、反省することはしばしばあります。それは次への糧となるからです。
私は60代になるまで、裸一貫でやってきたという自負から、成功も失敗もすべて自分の力と責任によるものだと考えていました。今思えば、それは大変な傲慢であったと気づかされます。ある時、自分の成功は決して自分一人の力ではなく、目に見えない多くの人々の助けがあってこそ成り立っているのだと悟りました。その瞬間から、自分は「生きている」のではなく「生かされている」のだと心から実感するようになり、残りの人生を社会のためにどう使うべきかを考えるようになりました。それが、「きずな育英基金」設立の直接的な動機となりました。
格差社会への挑戦としての「きずな育英基金」
私が代表を務める梅ヶ枝中央法律事務所は、1973年に12 坪の小さな事務所から始まりました。幸いにも多くの方々に支えられ、現在は弁護士37名を擁する組織となり、東京と京都にも事務所を構えています。事務所が大きくなるにつれ、企業法務なども手掛けるようになりましたが、私の心情の根底にあるのは、依頼者に寄り添う「依頼者ファースト」の精神です。
そして、その精神を社会貢献活動として具現化したのが「きずな育英基金」です。この基金を設立して12年になりますが、今日まで活動が順調に続いているのは、深刻化する社会のニーズ、すなわち「格差」の問題に応えるものだったからだと考えています。
資本主義社会において、競争の結果として差がつくこと自体は避けられないかもしれません。問題なのは、スタートラインが不平等であることです。経済的な格差が教育の機会の格差を生み、それが次世代にまで連鎖し、固定化されています。私は、誰もが同じスタートラインに立てる機会の平等を確保しない限り、真に公正な競争はあり得ないと考えています。
日本における貧困は、絶対的貧困ではなく「相対的貧困」として現れます。これは、国民の平均所得の半分以下で暮らす人々の割合を指し、全体では6人に1人、ひとり親家庭に至っては2人に1人がこの状況にあります。多くの子どもたちが、経済的な理由で夢を諦めざるを得ない状況に置かれているのです。

才能を開花させるための支援
きずな育英基金は、単なる経済的支援を目的とした奨学金制度とは一線を画しています。私たちの目的は、経済的な困難の中で埋もれがちな子どもたちの潜在能力を引き出し、その才能を開花させる後押しをすることです。
選考にあたっても、学校の成績が優秀であることや、文化・芸術・スポーツの分野で優れた実績を持つことを基準としています。これは、支援を受けた子どもたちが、将来それぞれの分野で社会を牽引するリーダーとして活躍してほしいという強い願いを込めて「奨学」ではなく「育英」という言葉を使っている理由でもあります。
基金は設立にあたって投じた私財に加え、この活動の趣旨に賛同してくださる方々からのご寄付や、遺贈によって支えられています。中には、全く面識のない札幌の老婦人が、遺産の一部を当基金に寄付してくださったという事例もありました。使い道が明確で、弁護士が運営しているという信頼性が、こうした支援の輪を広げているのだと思います。
支援の好循環と未来への展望
きずな育英基金から巣立っていった子どもたちは、私たちの期待に応え、
それぞれの道で素晴らしい成長を遂げてくれています。毎年、大学に進学する卒業生の多くが、国公立大学や難関私立大学へと進んでいます。大阪大学の薬学部から大手漢方薬メーカーに就職した者、慶應大学や東京音楽大学へ進んだ者、神戸大学から京都大学大学院へ進み、今はコンサルティング会社で活躍する女性もいます。現在、医学部に在籍している学生も6名おり、数年後には医師として社会に貢献してくれることでしょう。
私がこの活動を通して最も喜ばしく感じているのは、支援を受けた子どもたちが、今度は自らが支援する側に回ろうとしてくれていることです。大学生になった卒業生がイベントを手伝い、後輩の相談に乗る。この「支援の好循環」が生まれつつあります。このサイクルが確立されれば、私がこの世を去った後も、この活動は永続していくのではないかと期待しています。
私は、事務所の理念として「努力をして成長はするけれども完成はない」という言葉を掲げています。これは企業活動も人生も同じで、これで終わりという頂点は存在しません。絶えず努力し、成長を続けることが大切です。子どもたちにはいつも「努力・感謝・奉仕」という三つの言葉を伝えています。まずは自ら努力すること。そして、努力できる環境にあることに感謝すること。最後に、その恩を社会に返す「奉仕」の精神を忘れないでほしい、と。
明治維新の時代、「財を残すは下、組織を残すは中、人を残すは上」という言葉があったそうです。財産を残すことよりも、次代を担う優れた人材を育てることこそが、私の責務であると信じています。きずな育英基金で育った子どもたちが、この国のために役立つリーダーとなってくれること、それが私の最後の夢です。
山田庸男先生プロフィール
- 昭和37年 市立天王寺商業高等学校卒業
- 昭和42年 関西大学法学部卒業 司法試験合格
- 昭和45年 弁護士名簿登録
- 昭和48年 山田法律事務所設立(梅ヶ枝中央法律事務所)
- 平成6年 大阪弁護士会副会長
- 平成8年 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
- 平成9年 なみはや銀行金融整理管財人
- 平成19年 大阪弁護士会会長(日本弁護士連合会副会長)
- 平成20年 日本CSR普及協会近畿支部支部長
- 平成25年 一般財団法人梅ヶ枝中央きずな基金設立
magazine
社内報
新日本ビルサービス 社内報109号 2025年12月10日 32頁 1, 社長メッセージ2, 事業所紹介シリーズ センコーグループ 浦和物流センター 様3, 新日本グループ創立記念式典・永年勤続表彰4, さわやかインタビ…
当社は、さいたま市の“さいたまロードサポート制度”に参加し、本社近くの東大宮駅前メインストリート沿いで花壇の維持管理を行っています。 ↑見沼区の職員さんご協力のもと、お花を1つずつ植えていきます。 5月・11月に花の植え…
令和7年7月29日(火) 医療法人社団 厚済会 会長 花岡 加那子 様 生い立ちと転機 ― 花岡会長の生い立ち、学生時代のエピソード、大きく影響を受けたことや転機となったことをお聴かせください。― 私は生まれも育ちも…
company
会社案内
recruit
採用情報
資料ダウンロード
新日本ビルサービスのビルメンテナンス・
感染対策清掃・施設運営などにご興味をお持ちの方のために、
サービス内容をまとめた資料をご用意しております。




